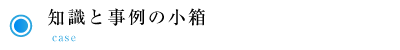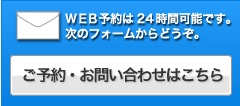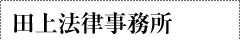Q 母が亡くなった後、兄から、兄に全ての遺産を相続させると書かれた遺言を見せられました。しかし、この遺言の作成日当時、母はすでに重度の認知症を患っていたはずで、兄が誘導して書かせたものだと思われます。このような場合、遺言の効力を争えますか。
A この遺言は「遺言能力」がない状態でなされたものであり無効である、という主張をすることができる場合があります。
遺言者は、遺言の内容を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(遺言能力)を有していなければならず(民法963条)、この「遺言能力」を欠いた状態でなされた遺言は無効となります。
遺言能力は、種々の考慮要素に基づき、事案ごとに個別的に判断されます。主な考慮要素としては、以下のようなものが考えられます(東京地方裁判所平成16年7月7日・判タ1185号291頁)。
①遺言の内容
②遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移
③発病時と遺言時との時間的関係
④遺言時と死亡時との時間的間隔
⑤遺言時とその前後の言動及び精神状態
⑥日頃の遺言についての意向
⑦遺言者と受遺者との関係
⑧前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無
たとえば、①について見ると、設例のように、兄に全財産を相続させるという遺言は、その内容が単純で分かりやすいため、遺言者の知的能力が比較的低下している場合でも、遺言を有効とする方向に働きやすいといえます。
逆に、多数の遺産を列挙して相続人ごとに異なる比率で配分しているような遺言は、内容が複雑で分かりにくいため、遺言を無効とする方向に働きます(大阪高等裁判所平成19年4月26日・判時1979号75頁など)。
また、⑤が着目される例を紹介します。
たとえば遺言者が介護サービスを受けていた場合、担当者が遺言者の状態について詳細な記録を作成していることが考えられます。これに記された遺言者の言動等は、遺言能力を判断するための重要な証拠となりえます(東京高等裁判所平成21年8月6日・金商1436号84頁では、デイケア利用時の遺言者の言動が詳細に認定され、遺言を無効とする判断が下されています。)。
また、公正証書遺言を作成する際は、公証人が遺言者にその内容を読み聞かせる(口授する)必要がありますが、たとえばその全文を一気に読み聞かせ、遺言者がこれに単純な返事をしたに過ぎなかった場合などは、遺言を無効とする方向に考慮した例があります(東京地方裁判所平成11年11月26日・判時1720号157頁)。他方、読み聞かせの際に遺言者が修正事項を適切に指摘していた場合や、公証人が事前に遺言者と面会をしたうえで遺言能力に問題はないと判断していた場合では、遺言を有効とする方向に考慮されています(東京高等裁判所平成15年12月17日・金法1708号46頁、東京地方裁判所平成20年10月9日・判タ1289号227頁)。
⑦はどうでしょうか。たとえば、母の生前、兄だけは母と同居してよく世話をしていたのに対して、他の相続人は母と関係が薄かったという場合、母が兄に全財産を相続させることを考えたとしても不自然ではなく、遺言を有効とする方向に働きます。
他方で、平時はほとんど会うこともない遠縁の親戚に、遺産の大部分を譲るという内容の遺言がある場合には、通常、かなり不自然な行動といえますから、遺言を無効とする方向に働きます(名古屋高等裁判所平成5年6月29日・判タ840号186頁)。
以上のように、遺言能力の判断においては、遺言者の医学的な知的能力(上記②)のみならず、その他の周辺事情も大いに考慮されます。そのため、遺言の有効性を争う際は、できる限り多くの客観証拠を集めた上、①~⑧に関する事情を立証し、説得的な主張を組み立てる必要があります。